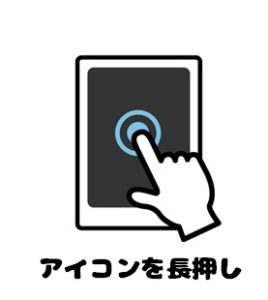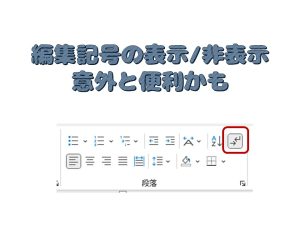7月1日「半夏生」──季節の節目に心を整える
本日7月1日は「半夏生(はんげしょうず)」です。あまり耳慣れない方も多いかもしれませんが、日本の季節を表す「雑節(ざっせつ)」のひとつで、夏至から数えて11日目にあたる日、本来夏至から11日目ですと7月2日ですが、現在では、半夏生は、太陽が黄経100度を通過する日として定義されているため、今年は7月1日となります。
昔の日本では、半夏生までに田植えを終えるのが良いとされてきました。この日を過ぎてから田植えをすると、稲の生育が悪く秋の収穫時期までに実らず、十分な収穫につながらないといわれ、農作業を一段落させて体を休める区切りの日とされてきたのです。関西地方ではこの日に「たこ」を食べる習慣(ちょうどこの頃たこがおいしくなる)があり、「たこの吸盤のようにしっかり根を張って育つように」という願いが込められています。
「半夏生」という言葉には、植物の名前も含まれていますが、実はこれには2種類の植物が関係しています。
まず、「半夏(はんげ)」とは、サトイモ科の多年草「カラスビシャク(烏柄杓)」のことを指します。この植物は、古くから漢方薬の生薬として「半夏」と呼ばれ、咳止めや吐き気止めなどに用いられてきました。このカラスビシャクが生え始める時期にちなんで、「半夏生」という節目の名前が付けられたとされています。
もうひとつ、「半夏生」とはドクダミ科の別の植物の名前でもあります。正式には「ハンゲショウ(半夏生)」という名で、葉の一部が白くなり、まるで化粧を施したように見えることから「半分化粧」→「半化粧」→「半夏生」と呼ばれるようになりました。梅雨の終わりの湿気の中、ひっそりと咲くその姿はとても涼しげで、日本の風情を感じさせてくれます。
半夏生の下には蛇がいるという言い伝えを聞いたことがあるかもしれませんが、調べて見ると
”半夏生(はんげしょう)の頃に、蛇のような形をした植物「カラスビシャク(烏柄杓)」が生えることから、「半夏生の下には蛇がいる」という言い伝えがあります。これは、カラスビシャクの仏炎苞(ぶつえんほう)が蛇の頭のように見えるため”
というAI概要が出てきました。今まで半夏生を見ると、蛇がいるのでは?!とドキドキしていましたが、何十年も前に聞い事が払しょくされて、すっきり、ホッとしました。
さらに今日は、もうひとつの大きな意味を持っています。
それは「一年の折り返しの日」であるということ。(1月1日から数えて182日目、明日が折り返し日となりますが折り返し月の1日目)。前半を振り返り、後半をどう過ごすかを考える節目としても、ぴったりのタイミングです。
私たちパソコン教室でも、前半の半年間、たくさんの方が新しいことに挑戦し、パソコンやスマホの操作を身につけてこられました。「もう年だから…」と最初は不安そうにされていた方々が「スマホを使いこなしたい」「写真をパソコンで整理したい」「Zoomで孫と話したい」──そんな想いを胸に、少しずつ自信をつけてこられました。
できる!が増えた皆さんの姿を見るとスタッフ一同、感慨深い思いになります。
後半の半年も、皆さんの「やってみたい!」という気持ちに寄り添いながら、もっと楽しく便利に、デジタルを味方にできるよう、私たちスタッフも心を込めてサポートしてまいります。
ちょっとした季節の行事に目を向けることで、節目を感じられ、日々の暮らしも豊かになりますね。
今日はそんな「半夏生」。空を見上げ、風に揺れる木々を眺めながら、折り返しのこの日、自分の歩みも少し立ち止まって見つめ直す日にしてみてはいかがでしょうか。