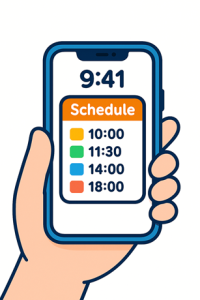今日は、「苗字の日」
今日は、「苗字の日」です。日本では9月19日が「苗字の日」とされています。普段あたりまえのように使っている苗字ですが、その歴史をたどると、意外と新しい文化であることがわかります。この日は、自分の名前や家族のルーツに思いを寄せるきっかけになる大切な記念日です。
日本で苗字が生まれたのは、飛鳥時代から奈良時代にかけてのことです。当時は「姓(かばね)」と呼ばれ、豪族たちが血筋や地位を示すために使っていました。しかし、それは支配層や武士など一部の人々に限られており、庶民は苗字を持たずに名前だけで生活していました。
庶民が正式に苗字を名乗れるようになったのは明治時代です。1870年、政府がすべての国民に苗字を名乗ることを許可しました。さらに1875年、苗字の使用を義務づける「平民苗字必称義務令」が出され、日本人全員が苗字を持つことになりました。この1870年9月19日、「平民苗字許可令」が公布されたことを記念して、9月19日が「苗字の日」とされています。
現在、日本には約30万種類以上の苗字が存在すると言われています。中には一部の地域にしかない珍しい苗字もあれば、全国的に広く使われている苗字もあります。実際の苗字ランキングを見てみると、日本人に親しまれている名前がよくわかります。
【日本の苗字ランキング(上位5位)】
1位 佐藤(さとう)
2位 鈴木(すずき)
3位 高橋(たかはし)
4位 田中(たなか)
5位 伊藤(いとう)
これらは東日本や中部地方を中心に多く見られる苗字です。佐藤は「藤原氏」に由来し、鈴木は紀伊国(和歌山県あたり)の信仰と関係があると言われています。また「田中」「高橋」などは地形や暮らしの様子に由来しており、農耕文化と深い関わりを持っています。苗字の意味を知ると、自然や歴史とのつながりが感じられますね。
苗字の日には、自分や家族の名前について調べてみるのがおすすめです。インターネットで苗字の由来を検索してみたり、家族と先祖の話をしてみたりすることで、普段は意識しない自分のルーツを発見できるかもしれません。また、珍しい苗字の人に出会ったら、その由来を聞いてみるのも楽しい交流のきっかけになります。

「苗字の日」は、明治時代にすべての人が苗字を持てるようになったことを記念する日です。苗字は家族や地域の歴史を映し出す大切な文化であり、私たち一人ひとりのルーツを示すものでもあります。9月19日には、ぜひ自分や家族の苗字に込められた意味を調べ、名前のありがたさを再確認してみてはいかがでしょうか。